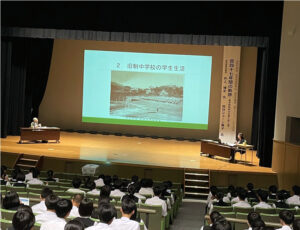第1161回 「郷愁の駄菓子屋さん」
5月31日
ある日、知らない町を歩いていたら突然現れた駄菓子屋に驚き、店の中に入ってみたら子どもの頃に売っていた駄菓子やプラモデルが、あの当時のままの値段で売っていて、まさに時間が止まったような空間だった…。
駄菓子屋の時代設定は、昭和40~50年代。色あせたロッテ・ガーナチョコレートの看板は「神崎商店」。店頭の古びたアイスのケース、店の中にはたくさんの吊された駄菓子が見えます。夕焼けの迫る路地には旧式の四角い車が影を落として、やんちゃ坊主たちが走り抜けていく足音が聞こえるー。
そんな懐かしい心象風景とも言えるこの駄菓子屋さん。実は、四万十町の海洋堂ホビー館で展示されている、ジオラマなんです。
『リアルを超えるリアリティ 【特別展】超絶技巧!!ジオラマ・ミニチュア作家展』情景師アラーキーこと、荒木智(あらき・さとし)さんの作家独立10周年記念展の作品に、心を奪われました。近所にあった駄菓子屋がいつの間にかコンビニに建て替わっている状況に危機感を感じて、「理想的な駄菓子屋をジオラマで残そう」と思い立ったとか。
この作品の全景は、こうなっています。
ものすごく、リアルでしょう!?木造家屋の造り、道路のアスファルトの加減、昔の路地の再現率に圧倒され、「これはすごい!」と写真を撮っていきました。今回、コラムにするときに、ふと「これに時間の要素を加えたら、どうなるだろう?」と思いつき、苦労して苦手な写真加工をしたのが、1枚目です。
アップにしても、リアルな店舗にしか見えません。引き戸のガタつきまで聞こえそうなほど、細部まで作り込んであります。
「20円」という値札のお菓子や、ブロマイド、プラモデルなど所狭しと並んでいます。
かつて子どもたちの夢がたくさん詰め込まれていた、この小さな愛おしい空間。
右側に回ると、ちゃんと内部も作り込まれています。
1階は駄菓子屋のおばちゃんがいる和室に、「そうそう、昔はこんな感じだった」と つい独り言。
2階の木造のベランダは、空色のビニールをかけた物干しなどの生活感までリアルですよね。
反対側から見たお店。昭和の雑多な路地の雰囲気をここまで再現できるなんて…。
作者のアラーキーさんは、1969年東京生まれ。現存している駄菓子屋さんを取材し、昭和の商店建築の基本を勉強して、このジオラマを作り上げたそうです。リアリティーを出すために建築的な知識以外にも法律的な知識、その時代の文化などを調べながら作るのはとても難しく、また楽しいことだとか。
この駄菓子屋の制作方法や駄菓子屋の知識解説は、『駄菓子屋の【超リアル】ジオラマ』という1冊の本にまとめられたそうです。早速、注文してしまいました。
実際にご覧になりたい方は、海洋堂ホビー館四万十で、6月29日(日)までの開催ですので、ぜひどうぞ♪